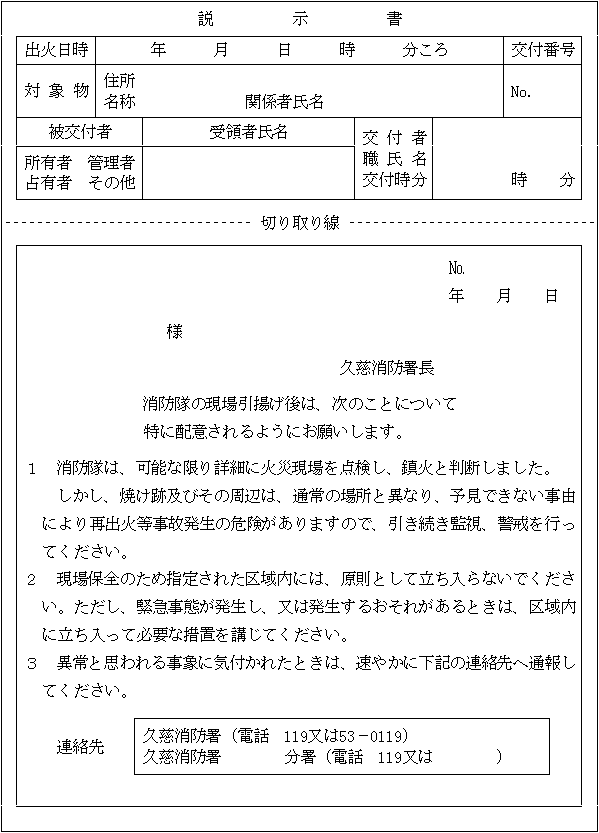 様式第2号
様式第2号
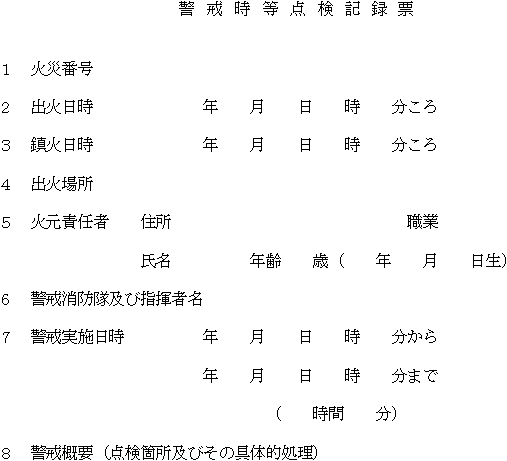 様式第3号
様式第3号
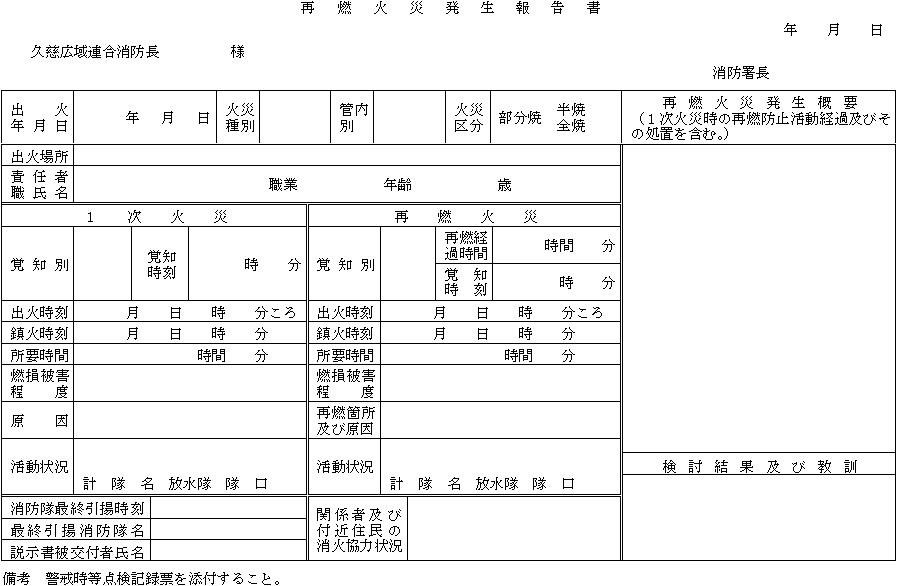
○再燃火災防止規程 平成20年4月1日消防本部訓令第12号 再燃火災防止規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、再燃による火災の絶無を図るため、再燃火災の防止に関し必要な事 項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 再燃火災 消防隊が消火活動を行い引き揚げた後、再び消火の必要がある燃焼現 象をいう。 (2) 警戒 消防隊が現場を引き揚げた後、再燃火災の発生を未然に防止するため、随 時火災現場に出向し、再燃火災防止活動を行うことをいう。 (指揮者の責務) 第3条 消防長又は消防署長が指名する者(以下「指揮者」という。)は、各消防隊を指 揮監督して消火活動を行い、再燃火災の発生を防止しなければならない。 (再燃火災防止の活動) 第4条 消防隊の隊員は、別表の再燃火災防止活動基準(以下「基準」という。)に定め るところにより、再燃火災を防止するための活動を行わなければならない。 (破壊作業) 第5条 基準により破壊作業をするときは、努めて関係者の承諾を得て行うものとする。 (関係者に対する説示等) 第6条 指揮者は、消防隊が火災現場を引き揚げるときは、再燃火災防止のため必要のあ る建物の関係者に説示書(様式第1号)を交付し、再燃火災の防止について協力を求め なければならない。 (警戒) 第7条 指揮者は、次に掲げる場合は、消防隊に警戒を行わせなければならない。 (1) 建物火災又は林野火災で、気象の状況により火災警報、乾燥注意報又は強風注意 報のいずれかが発令中のとき。 (2) 建物火災のうち、建物の構造が木造及び防火造の場合で、小屋裏、天井、壁体内、 床面等の未燃焼部分に焼け止まりがあるとき。 (3) 燃損物品の危険物、準危険物、特殊可燃物、高圧ガス、液化石油ガスその他再燃 のおそれのある物品で、当該物品が多量にあるとき。 (4) 関係者等の不在によって、立会い又は承諾が得られないため未確認部分があると き。 (5) その他指揮者が必要と認めたとき。 (警戒時の点検) 第8条 前条の規定により警戒を行う者は、基準に定めるところにより点検を行わなけれ ばならない。 (警戒の解除) 第9条 指揮者は、再燃のおそれがないと認めたときは、警戒を解除するものとする。 (点検記録) 第10条 第4条又は第8条の規定に基づいて活動又は警戒を行った消防隊の指揮者は、警 戒時等点検記録票(様式第2号)に記録しなければならない。 (報告) 第11条 消防署長は、再燃火災が発生したときは、再燃火災発生報告書(様式第3号)に 警戒時等点検記録票の写しを添えて、直ちに消防長に報告しなければならない。 附 則 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 別表(第4条関係) 再燃火災防止活動基準 1 建物火災の場合
区分 | 留意事項 | 活動着眼点及びその点検処理方法 |
部分 焼 | 1 建物評価額の20 %未満の焼損状況 で比較的焼損範囲 が局部的であり、 再燃防止を意図と する処理活動の徹 底により、再燃危 険は著しく減少さ れる。 2 再燃火災防止活 動に際しては、建 物関係者の協力又 は承諾を得るとと もに再燃に係る事 後管理及び措置の 徹底を図る。 | 1 床面 (1) 畳面は、畳の合せ目、敷居等の木部の接続部 を点検し、焼け焦げ部分があるときは、床板を確 認するとともに、必要に応じて畳等を屋外の安全 な場所へ搬出し、必要な処理をする。 (2) 畳以外の床面で燃え抜け等を生じている部分 には、根太等の床組構造材まで点検し、焼け止ま りを確認し、必要な処理をする。 2 壁体 (1) 木造の壁面は、焼け焦げであっても、壁材合 せ目及び壁体内部を点検し、必要な処理をする。 (2) モルタル、耐火ボード等の不燃材で構成され る壁体は、火源探知が困難であるため、素手によ る表面温度差等によって勘案し、必要とあれば壁 体上部を小破壊し、必要な処理をする。 (3) 焼損した壁面に位置する押入れ、天袋等の内 部及びその内容物を徹底して点検し、必要な処理 をする。 3 天井及び小屋裏 燃え広がりが天井に至っている場合は、必ず天井 板(耐火ボードを含む。)を小破壊して小屋裏まで 点検し、必要な処理をする。 4 その他 (1) 居室内等建物内部に焼き炭化物を集積放置す ることなく、屋外の安全な場所へ搬出し、必要な 処理をする。 (2) 外見上火源視認が困難な箇所及び布団等の消 火困難な焼き物については、状況により必要な点 検及び処理をする。 (3) その他前2号以外の箇所及び焼き物品につい ては、状況により必要な点検及び処理をする。 |
半焼 | 1 建物評価額の20 %以上70%未満の 焼損状況で焼け止 まりが随所に存在 する建物は、徹底 した再燃火災防止 活動を欠くことに より、極めて再燃 危険が大である。 2 建物関係者に説 示書を交付し、破 壊作業等を含む再 燃火災防止活動の 理解を求め、更に 事後管理について 協力を依頼する。 3 建物関係者が不 在の場合には努め て警察官等と協議 の上、必要かつ適 正な措置を講ずる。 | 1 床面 (1) 床板等部分が焼失している場合は、その下低 部の床組構造材及び焼き堆積物を点検し、必要に 応じて堆積物等を取り除き処理する。 (2) 床板の一部が残存している場合は、床面の焼 け止まり及び床板裏面を点検し、必要な処理をす る。 2 壁体 (1) 焼け止まり状況を呈する木製、モルタル、耐 火ボード等の二重壁については、火源確認及び消 火死角面であるため、必ず壁体内部を小破壊し、 点検処理する。 (2) 壁体面に据え置かれている家具等の背面及び 押入れ、天袋等の内部は、注水死角面でもあるこ とから、速やかに点検し、必要な処理をする。 (3) 外壁面のモルタル、亜鉛引鉄板張等の内部は、 素手で触れる等して火源を確認し、小破壊し消火 する等必要な処理をする。 (4) 外壁の戸袋内部及びその周辺についても点検 し、必要な処理をする。 3 天井及び小屋裏部分 壁体から燃え広がりを呈している場合には、天井 との接続部分及び小屋裏を点検し、必要な処理をす る。 特に小屋裏の点検については、燃焼状況にもよる が野地板及び棟木を重視する。 4 その他 (1) 床面に落下した亜鉛引鉄板等の主構造材の下 方にある焼き物を点検し、必要な処理をする。 (2) 布団等の綿花類、マット、畳くず、木くず、 ゴムくず、紙類その他消火困難な物品は、状況に より屋外等の安全な場所へ搬出し、必要な処理を する。 (3) 火災状況により放射熱及び飛火による隣接棟 への延焼に留意し、適切な火源確認を実施し、必 要な処理をする。 (4) 部分焼区分に準拠し、点検処理する。 (5) その他上記以外の箇所及び焼き物品について は、状況により必要な点検及び処理をする。 |
全焼 | 建物評価額が70% 以上の焼損状況の建 物は、焼き残存物部 分を重点的に処理す ることにより、再燃 危険は取り除かれる。 | 全般 (1) 床面、壁体及び構造材の残存部分焼け止まり を点検処理する。 (2) 落下及び残存している各構造材のほぞ組部分 を点検処理する。 (3) 瓦、亜鉛引鉄板その他構造材を取り除きなが ら下方部の堆積焼き物を点検し、必要な処理をす る。 (4) 部分焼及び半焼区分に準拠し、点検処理する。 (5) その他上記以外の箇所及び焼き物品について は、状況により必要な点検及び処理をする。 |
2 林野火災の場合
留意事項 | 活動着眼点及びその点検処理方法 |
1 焼け止まり線に止まる ことなく広範囲に、かつ、 綿密に火源を探索し、徹 底処理する必要がある。 2 指揮者は、隊員の安全 管理に着意するとともに、 相互協力を基調とし効率 的活動に留意すること。 | 1 地表面に一部露出する立木の根株等は、その表裏を 確認し、更に必要があれば地表下部分も発掘し、必要 な処理をする。 2 山林内に放置された廃材等は、極力排除して必要な 処理をする。 3 枯草及び枯葉の八重状に積み重なった部分は、特に 確認し、必要な処理をする。 4 老木、枯木等の空洞部分は、確認し、必要な処理を する。 5 その他近隣に家屋等がある場合は、その方面を確認 し、必要な処理をする。 |
3 車両等の火災の場合
留意事項 | 活動着眼点及びその点検処理方法 |
車両及び航空機火災の活 動については、燃料の漏え い等に留意し、安全管理を 図ること。 | 1 発煙源を徹底して点検処理する。 2 発生場所等を勘案し、注水をもって深部まで消火処 理する。 3 その他上記以外の箇所及び焼き物品については、状 況により必要な点検及び処理をする。 |
様式第1号様式第2号
様式第3号